農業経営の継承とは
農業経営における事業継承とは、農地・機械・施設等の有形資産とともに、技術・ノウハウ・人脈等の無形資産を次の世代の経営者に引き継いでいくことです。
円滑な経営継承を実現するためには、経営者と後継者による話し合いだけではなく、後継者の育成も必要となるため、計画的に時間をかけて取り組む必要があります。病気や加齢で農業が続けられなくなってから取り組むのではなく、早めの対応を心がけましょう。
経営継承の3つのタイプ
経営継承には以下の3つのタイプがあります。
それぞれのメリットやデメリットを理解し、継承に必要なことを整理しましょう。
親族内継承
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
従業員継承(法人経営)
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
第三者継承
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
富山市の支援策
富山市では、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、農業の経営継承を支援する取組を行っています。
経営継承発展等支援事業
地域農業の担い手の経営を継承した後継者が、その経営を発展させる取組を行う場合に必要となる経費を国と一体となって支援します。
| 補助額 | 補助上限:100万円(国1/2、市1/2) |
|---|---|
| 補助対象経費 | 専門家謝金、研修費、機械装置費、広報費、開発費、委託費、外注費 等 |
| 主な要件 |
▪中心経営体等である先代事業者から、経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者であること ▪主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと ▪経営発展計画を策定し、当該計画に基づいて経営発展に取り組むこと |
とやま農業経営総合サポートセンターによる専門家派遣
経営継承をはじめとした多様な経営課題の相談に応じるため、支援チームを構成し専門家派遣等の支援を行います。
| 支援内容 |
関係機関との面談を経て、専門家派遣を無料で実施します。専門家への謝金等の支払いは、とやま農業経営総合サポートセンターが全額負担し、事務手続きもすべて行います。農業者の皆様の負担はありません。 ※ただし、支援終了後において引き続き専門家から指導等を受けるために必要となる顧問料、当専門家が指導を行う際に要する材料費等は、当該指導を受ける農業者の負担となります。 |
|---|---|
| 登録専門家 | 税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、司法書士、不動産鑑定士、事業承継士 等 |
経営継承の事例紹介

株式会社 ミルクリエイト
北川 清貴さん
概要
| 継承年月 | 令和2年11月 |
|---|---|
| 経営規模 | 乳牛40頭 |
| 従業員数 | 家族従事者(正規)2名、アルバイト2名 |
経営継承までの流れ
- 平成 12年〜
- 実家(酪農)で就農開始
- 平成 22年〜
- 酪農ヘルパーとして従事開始
- 令和2年11月
- 経営開始
- 令和6年11月
- 法人化
経営継承のきっかけ
実家が酪農農家だったので、初めは実家の酪農経営を手伝っていました。その後、酪農ヘルパーとして人手不足で困っておられる様々な酪農農家さんのもとで働き始め、その中のお一人の酪農農家さんから、後継者にならないかというお話をいただいたことで、その方の経営を継承することを決めました。
経営権の継承について
酪農ヘルパーとして働き始めてから経営継承するまでの間のうち数年間、継承元の農家さんの元で継続的に従事し、技術を習得していきました。継承を決めたのは継承の1年前の令和元年で、それから経営開始までの間に様々な機関のサポートを受けながら、手続きを進め、令和2年11月のタイミングで開業届を提出しました。
継承時の相談先
就農するにあたり、主な相談先は富山広域普及指導センターでした。活用できる補助金や支援制度等を教えてもらったり、資産や税務、資金調達等のことに関しても、税理士や司法書士へ相談をする場を設けてもらったりと、総合的に継承をサポートしていただきました。
資産の継承について
農地、施設、機械の継承
継承するにあたって、まず初めに農地や施設、機械について、購入するのか賃借するのかを広域普及指導センターのご担当者さんにご相談し、税理士や司法書士も含めて話し合い、購入することに決めました。
販路、取引先の継承
継承元の農家さんから、人との付き合いは大事にしてほしいというお言葉があったことから、継承前と同じ取引先の方々にお願いしています。
生産に関する技術の継承
技術的なことは継承元の農家さんや、その他のヘルパーとして従事した先の酪農農家さんに相談し、中でも新規で独立就農しておられる農家さんには度々様々なことをご相談しました。
経営継承後とこれから
酪農は生き物を育てる産業のためなかなか休みが取れないことや、機械に故障等のトラブルがあり、出荷ができないことになると、精神的、金銭的なダメージがすべて自分に降りかかってくるという大変さはあります。それでも、自分達自身が毎日精一杯作業をして生産した牛乳を地域の人が飲んでくれているということを実感できることが、酪農ヘルパーとして他の農家さんのお手伝いとして働いていた時には感じられなかった喜びで、自分で経営をやっていてよかったと強く感じます。
第三者継承で、さらに地元ではない場所での就農だったため、始めの頃は地域の方々とのお付き合いで、気を使うことはありましたが、営農していく中で徐々に周囲の農家さんとの関係を構築していき、理解を得られるようになりました。今は酪農作業の合間に近隣の営農組合の一員として、水稲の農作業にも従事したり、耕畜連携を行い事業を活用したりとお互いに協力しながら営農することができています。お世話になっている方々のためにも、これからは地域に貢献できるように頑張っていきたいです。

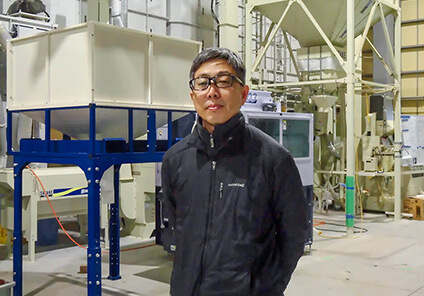
株式会社 茶木農場
茶木 俊文さん
概要
| 継承年月 | 平成 25年1月 |
|---|---|
| 経営規模 | 水稲48ha、大豆8ha、WCS6ha |
| 従業員数 | 家族従事者(正規)2名、家族従事者(アルバイト)2名、正社員2名 |
経営継承までの流れ
- 平成 24年3月
- 退職
- 平成 24年4月〜
- 先代経営者(父)のもとで就農開始
- 平成 25年1月
- 経営開始
- 平成 30年1月
- 法人化
経営継承のきっかけ
実家は専業農家だったので、小さい頃は農業を手伝っていました。でも農業をやるつもりはなく、大学卒業後は一般企業に就職しました。ただ、両親が高齢化していく中で、直接言われたわけではありませんでしたが、何となく家業を継がなければならないな、という思いはありました。そうした中、もし農業を始めるなら35歳くらいまでだろう、という思いもあり、勤めていた企業を辞めて、父のもとで農業をやっていくことにしました。
経営権の継承について
退職後1年間は父のもとでともに作業し、技術を習得していきました。1年後、個人事業主としての開業届を提出し、出荷名義を父から自分に変えるところから、継承を始めました。ただ、農業経営は仕事がかなり多岐にわたるので、いきなりすべてを自分でやったわけではなくて、父と一緒に作業をしながら、仕事のレベルに合わせて徐々に仕事を任せてもらった、というかたちです。地主さんや地域の農業者との関係は、地域で営農する中で徐々になじんでいきました。
資産の継承について
農地の継承
父の所有地については、農地の名義は父のままですが、農地法3条の使用貸借手続きをして、権利設定をしました。法人化後は、個人から法人への賃貸契約を締結しています。
施設、機械の継承
最初は父名義でしたが、新しく導入するものから順次自分の名義にしていきました。
金融資産の継承
父名義の融資があったので、自分に名義変更して返済しました。
生産に関する技術の継承
父と一緒に作業する中で、口伝で学んでいきました。その他、手の空いた時期や冬季などに、研修会に参加し、栽培技術や農業経営について学んでいきました。
継承時の相談先
就農するにあたり、主な相談先は富山農林振興センターでした。活用できる補助金や支援制度等を教えていただきました。また、青年農業者協議会も紹介していただいて、その活動の中でも研修会や農業者の仲間づくりをする機会を得ることができました。
経営継承後とこれから
経営継承後、受託面積が徐々に増えてきて、人手も施設も足りなくなってきました。これから面積を拡大して経営を発展させていくなら、組織や運営の仕組みを整えて行こうという思いから、継承5年後に法人化しました。その後、従業員の雇用、乾燥調製施設の新設、GAPの取得…と、一つずつ先へ進んでいっている感覚です。
経営継承については、一見すると1年で準備期間が終わったように見えますが、実際は時間をかけて、徐々に入れ替わっています。特に農業については1年で1作というものが多く、技術を学ぶことや経営を安定させるには時間がかかると思います。これから経営継承を考えている人は、早めに動いたほうがいいと思います。稲作経営は食料生産基盤である農地を継承していくという点で他の産業と大きく違う所があります。このことから“次の世代へ経営を継承する”ことが目標になると考えています。私も喜んで引き継いでもらえるような経営を目指したいと思います。

お問い合わせ
-
富山市担い手育成総合支援協議会
富山市役所 農林水産部 農政企画課 - 〒930-8510 富山市新桜町7-38(富山市役所東館4階)
【窓口受付時間】月曜日~金曜日:午前8時30分から午後5時15分













